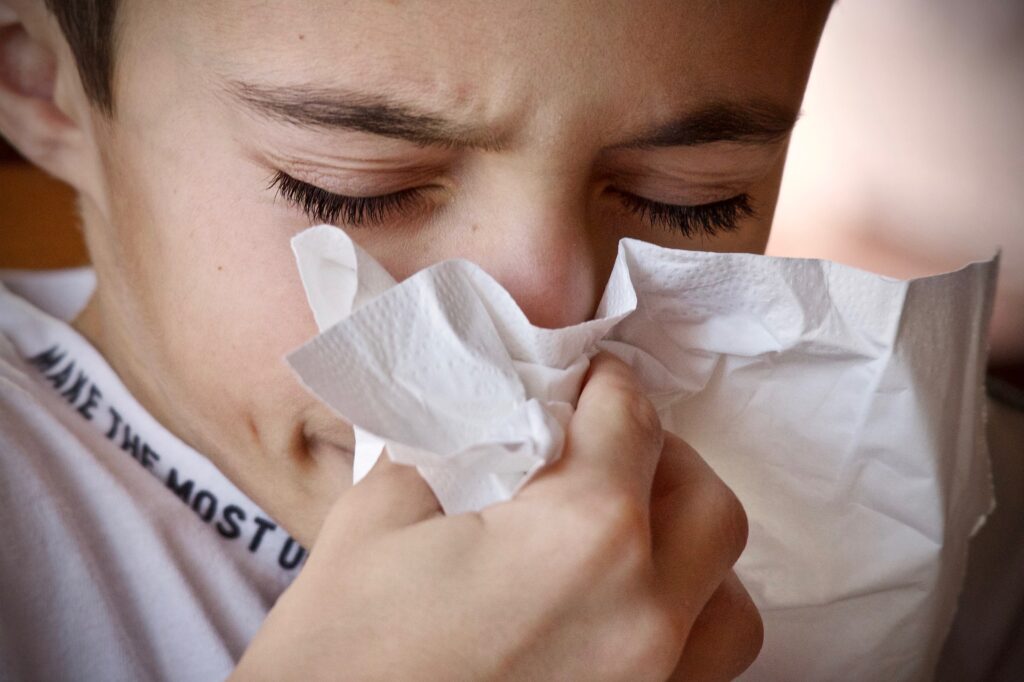お知らせチャーガのこぼれ話 #9
2022.02.23
北海道チャーガ(樺のアナタケ)

二十数年前札幌のススキノで飲んでいたら突然ホステスが黒い液体を持ってきた。
これを飲むと二日酔いにもならないし癌にも効くらしいと熱心に俺に説明を始めた。
そして私に飲ましてくれるのかと思いきや、そのホステスはその黒い液体を一気に飲み干して「これで明日二日酔いにならない」と呟いたのだった。
それが長い付き合いになるチャーガとの初めての出会いだった。
ホステスから説明を受けた後、ほどなくして札幌でチャーガブームが起こった。
ススキノで飲むといろんな席で黒い液体を見るようになった。
暫くブームは続いたように思う。
しかし北海道のローカル番組で「チャーガは癌に効果があると実証されてる訳ではありません」と有名アナウンサーが話した後、鎮静化に向かいブームは去った。
そんなブームが去った直後にチャーガの商品を販売することになったのだが、当初、モンゴル産・中国産・北海道産・ロシア産と作りいろいろ試した。
その中でエキスにして暫く常温保存して様子を見るテストをしてみた所、なんと最初にカビが発生したのが北海道産だった。
最後にカビが発生したのがロシア産。
なんと夏場常温でおいて一週間以上カビが発生しなかった。
チャーガの抗酸化力の強さを証明する実験となった。
残念ながら北海道産が最初に発生したのだが、その原因として北海道産は山で採取した後、除菌をする事も無く、そのままの状態で販売されているので、最初から鳥の糞等の菌が付着している為だと判明した。
それは今も変わらない。
よく道端の販売所・道の駅で採れたチャーガの塊を販売してるが、どのように採取したのですかと聞いてみると答えられる人がいない。「ただ山で採って来た」と言うだけです。
本来チャーガは秋に採取しなければいけないし、更に白樺にキノコの菌が付着して生育する期間が5年以上経過したものでなくては効能が低下すると言われている。
北海道では採取する専門業者がいないので林業に従事されてる方や、アルバイト的に採取するのが殆どだ。
そのような方は基本的なチャーガの知識も無く、ただ採取すれば良いと考えているので採取する時期の知識も無く、見つけたら手当たり次第に採取し、採取後も乾燥させて除菌する等、基本的な作業は行われていない。
チャーガを販売している業者でも基本的な知識がなくて販売している所があり驚くことがある。
北海道ではそのまま売っているチャーガは絶対に買ってはいけないと考えている。
前途したように商品化するための作業をしていない為カビも一緒に飲んでしまうことになる。
あのような業者は本当に無責任で正直怒りさえ覚える。
当社は全てロシアで長年チャーガの製品を作り続けた会社から輸入している。
ロシアは1960年代から総合病院にてチャーガの治験を約10年間数万人規模で実施して薬品にするまで研究してきた実績がある。
私もロシアに行き勉強してきたがチャーガに関しては「ロシア以外に商品として認められるものは無い」と言うのが私の実感だ。
北海道産のチャーガはそれ程までに全てにおいて差異が大きく比較にはならなかった。
皆様もチャーガを購入する際にはよくよく検討されて購入して下さい。
良い商品を購入されて皆様の健康に役立つチャーガを是非飲んで下さい〜。
お知らせチャーガのこぼれ話 #8
2022.02.16
アレルギー反応
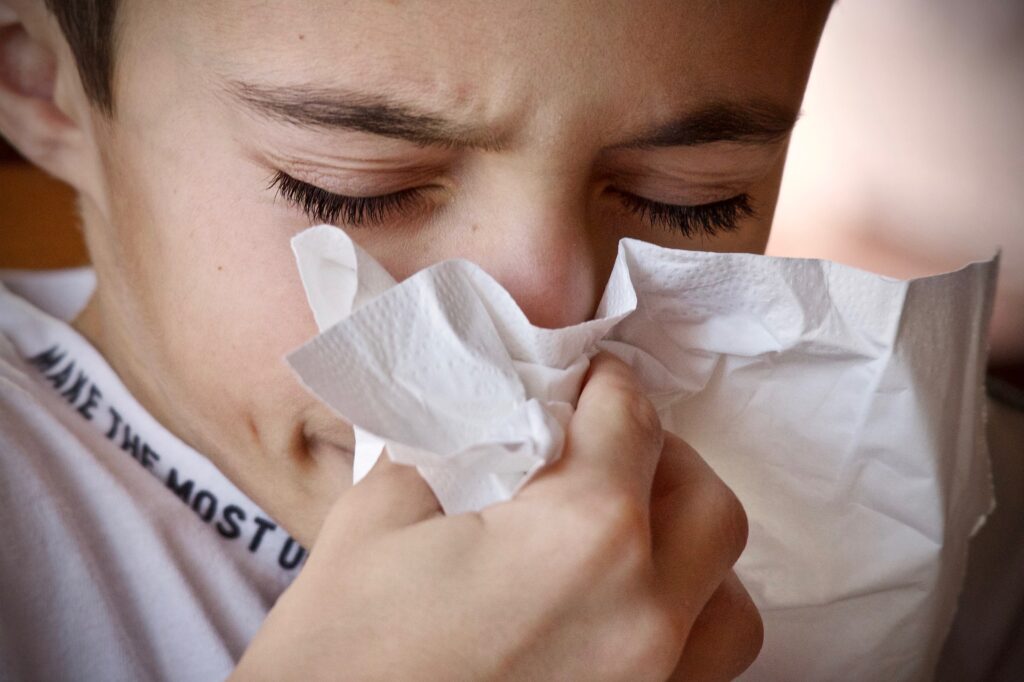
私の小さな頃の遊びは、山でかけっこやクワガタ捕り、海で貝を獲って焼いて食べたりしていた。
その時の貝がまた何とも美味しかった。
普段食べてるものとは違う貝に感じるほど美味だった思い出がある。
今の子供たちも体験すると大喜びすると思う。ディズニーランドも楽しいけれど自分で頑張って獲った物を食べるのは最高の経験だ!
一生の思い出になるほどの喜びと楽しさがある子ども達に体験して欲しいと心から思う。
とにかく自然の中で過ごす時間が多かったな~
そのせいか子どもの頃から花粉症になったことがない。
イギリスの研究で長男・長女にはアレルギーが多いとの結果が出た。
末っ子には少ないらしい。
少ない理由として最初の子は親が神経質に育てるせいか衛生的に完全な状態にしてしまうため細菌に触れる機会が少なすぎるらしい。
末っ子は親も慣れるし兄や姉から細菌をもらったりするためアレルギーや花粉症に対しての適応する能力ができると言われている。
ガンジス川で沐浴をするインドの人をテレビで見るけど、汚物も流れているような汚い川で沐浴して病気にならないのが本当に不思議に思う。
日本人なら一発で細菌にやられてアウトでしょ。
育つ環境で適応力が育まれるなら今の清潔にしすぎる生活も過敏すぎるのかもしれない。
正直なところ企業のCMに乗せられて必要以上に細菌のない生活を送らされている気がするな~
シンガポールで糖尿病の患者が急増した時期がある。
政府が原因を調べた結果暑い中運動する人がスポーツドリンクを飲みすぎるのが原因だと判明した。
シンガポール政府はスポーツドリンク飲みすぎの注意喚起をしたことがある。
市販の飲料水は砂糖の塊が液体になったと考えた方が良い。
人の体は糖質中毒に知らずになってしまい、糖質を摂取しないと物足りなくなるよう作られている。
余り他の商品を非難したくはないが、糖分の塊である飲料水は絶対とらない方がいいと断言できる。
特に子どもには飲ませないようにして頂きたい。
いろんな意味でアレルギーなどが増えていくのが現代社会。
予防の一つとしてチャーガは有効だ。
自己の体内環境を保つ力の作用がチャーガにはあるので結果としてアレルギーの予防になっている。
そろそろ花粉が沢山飛ぶシーズンになる。
国民の三人に一人は花粉症と言われる時代にチャーガで是非予防をしよう。
私の知人は鼻がムズムズしだしたらチャーガを飲むと止まると言っていた。
体内にチャーガの成分がある間は止まるみたいだ。
鼻がムズムズしたらチャーガを飲みましょう〜
お知らせチャーガのこぼれ話 #7
2022.02.09
食べ過ぎ

家の猫は体重11㎏もある巨漢である。メインクーンと言う品種で猫の中では身体が大きくなることでも知られている。
家の女房は溺愛をしていて私が死んでも良いが猫が死んだら私も死ぬと叫ぶ毎日である(笑)
その溺愛している猫がいきなり2㎏も痩せてしまったから大騒ぎ~。
病院に行って糖尿病と診断されたが、初期なので一日二度の食事にすることで改善できると先生から指導を受けたようだ。
それまではビュッフェではないけどいつも餌があり食べ放題だったので食べたいだけ食べていた。
そりゃ太るよな~
それが病気発覚後二回の食事になったら、まずうんちが臭く無くなった。
それまではなんの兵器かと思うぐらい臭くて、おなら爆弾をいきなり投下してきてよく悶絶させられていた。目ヤニもなくなりイケメン猫に戻った感じ。
食べ過ぎが猫の体にもいかに悪いかよくわかる。
昔から「腹八分に病なし」と言われるが本当にそうだと思う。
私見ではあるが、現代人の半数以上の病気の原因は食べ過ぎなのではないかと考えている。
日本人は古来より穀物中心の食生活であったのは良く知られている。
そのため栄養を腸で吸収するには長時間必要とされたようだ。
それが近年西洋的な食事の増加、特に肉食が多くなったせいで腸の中で消化しきれず食べ物が腐敗し、血液が汚れる現象が多くなっていると聞いたことがある。
漢方では2000年以上前から「万病一元、血液の汚れから生ず」という概念がある。
血液の汚れは万病の元と言えるのですが食べ過ぎ又は偏った食事が病気の元になっているのが現代人の特徴だと思う。
ちなみに私は一日二食だ。
もう何十年も二食生活なので、たまに三食食べると体が重くなりただでさえ頭が悪いのに余計に頭が回らない。
血液が消化のため胃腸に集中するからだろう。
お陰様で二食生活のせいか病気らしい病気をしたことがない。
ある程度の年齢になったら自分の体と相談して適切な食生活を目指すべきだと思う。
それに人間の免疫力は空腹時に大いに働くらしい。
ウィルスの脅威が猛威を振るっている今、過食は避けて適切な食生活で免疫力を上げたいものだ。
免疫力を上げると言えばチャーガだ。
さぁ今日も、免疫力向上の為チャーガを飲みましょう〜
お知らせチャーガのこぼれ話 #6
2022.02.05
花粉症

去年同級生にチャーガ茶を送ったところ10数年苦しんでいた花粉症が治ったかもしれないと連絡がきた。
「何故か鼻水も出ないし、咳もしないんだけどチャーガのお陰で症状が出ないのかな!?」と、興奮と、喜びと、驚きの電話だった。
チャーガで治ったかはさておき、苦しんでいた同級生に症状が出ないことに嬉しさが止まらなく、こちらも聞きながらいつの間にか笑顔になっていた。
体が辛いのは当人しか分からないものの、私も年齢を重ねるごとに若い時に感じられなかった体の変化を感じ健康の有難味の想いが増すようになった。
やはり一番大事なことは健康でいれる生活をすることだと思う。
つまり、”病気にならない予防生活”の事。
長年チャーガを販売して実感することは、色々と世の中には健康情報が溢れているけれど、
1.睡眠
2.運動
3.食生活
4.ストレス解消
が大事だと言うこと。
この4つのバランスが取れていれば病気になることは殆どないと思う。
出来れば体に良いと言われる物を毎日続けることが大切である。
チャーガもそうだし、他の物でもご自分の体に合うものを体内に取り入れよう。
何よりも継続が一番だ。
そんな意味でも今日もチャーガを飲みましょう~
お知らせチャーガのこぼれ話 #5
2022.02.01
神農本草経

中国最古の歴史書「史記」によると、古代中国の三皇五帝の一人に『神農(しんのう)』という者がいたそうだ。
神農は「百草をなめて一薬を知る。」と、あらゆる植物を自ら吟味し一日に70回以上も毒に合いながら身体におこる反応を自ら確かめ、薬用になるものを選び、人々に医療と農耕を教えたそうだ。
その事から「神農大帝」と尊称され「本草学」の始祖と言われた。
その名を冠した「本草書」が2000年前に書かれた「神農本草経」と呼ばれる書である。
この書、365種類の薬物が効能によって上・中・下の3種に分類されている。
上薬は120種類あり、無毒で生命を養い長期にわたって服用しても害はなく、薬草の中でも最高品質と呼ばれ、不老長寿を願う高貴な人々に使用されたと言わている。
チャーガは上薬に分類されている事から、古代の中国の人々の健康を守ってきたと考えらる。
それにしても古代の人々の薬学の知識の豊富さとその高い知識レベルには本当に驚かされる。
古代の中国では宇宙の星の数を60兆とし、「宇宙を凝縮した者」が60兆の細胞を持つ人体と考え、それを小宇宙と考えた。
ちなみに、人間の内臓を表す漢字には全ての部首に「肉月」がついているのをご存知ですか?
紀元前1000年頃から紀元前500年頃にかけてインドで編纂された「ヴェーダ」と言う一連の宗教文書では、「人は亡くなったら月へ向かい、月の関門を通ることができた魂は天国に行き、通れなかった魂はまた地球に戻る」とある。その為内臓には月の子どもという意味で肉月が付くと言われている。
私達は残念ながら天国には行けなかったらしい(残念)
今度は月の関門を通れるようにチャーガを飲みましょう(笑)